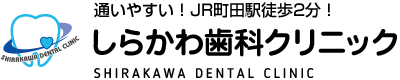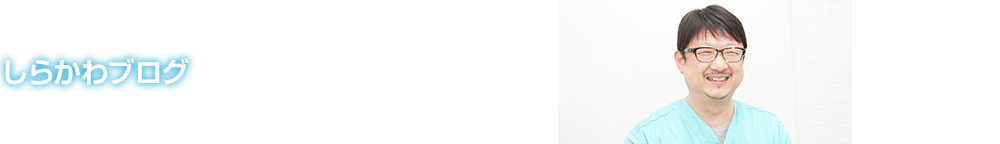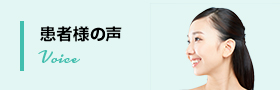寝ている時に呼吸が止まっていませんか?②
2024年4月26日 (金)
前回に続き、寝ている間の呼吸についてご紹介します。今回は睡眠時無呼吸症候群の種類や治療法について詳しくみていきましょう。
睡眠時無呼吸症候群は「閉塞型睡眠時無呼吸症候群」と「中枢性睡眠時無呼吸症候群」の2つに分けられ、それぞれ原因が異なります。閉塞型睡眠時無呼吸症候群は、気道が何らかの理由で狭くなり、息苦しくなったり呼吸が止まってしまうタイプです。気道が狭くなる原因として、肥満による首の脂肪の増加、低位舌、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎などが挙げられ、睡眠時は筋肉の緊張が解けることで気道が塞がれやすくなり、低呼吸や無呼吸状態を引き起こします。中枢性睡眠時無呼吸症候群は、呼吸中枢の異常によって引き起こされるタイプです。問題が脳にあるため、閉塞型睡眠時無呼吸症候群よりも改善が難しく、危険度も高い傾向にあります。
睡眠時無呼吸症候群の治療法としては「マウスピースの使用」と「CPAP(気道に空気を送り続ける治療法)」の2つが基本で、扁桃腺が明らかに肥大して気道を塞いでいるケースや気道が狭すぎるケースでは「外科手術」が行われます。睡眠時無呼吸症候群と診断される方のほとんどが「閉塞型睡眠時無呼吸症候群」ですが、だからといって安心できるものではありません。質のいい睡眠を習慣化するためにも、原因を明確にして正しく対処するようにしましょう。
カテゴリー: 豆知識
寝ている時に呼吸が止まっていませんか?①
2024年3月27日 (水)
睡眠中に呼吸が10秒以上停止している(無呼吸)、または換気量が半分以下になっている回数が30回以上、もしくは1時間に5回以上あれば「睡眠時無呼吸症候群」と診断されます。生活習慣の乱れが原因で発症しやすく、長期間続けば命の危険がある怖い病気です。
リスクの高い生活習慣は、ストレスによる喫煙習慣をはじめ、就寝前の飲酒や運動不足が挙げられ、肥満や高血圧の方、高脂血症の既往がある方はとくに注意しなくてはいけません。
また、女性よりも男性のほうが比較的なりやすく、自覚症状があまりないのが特徴です。
舌の位置異常や大きさも関係しており、舌が下顎全体に広がっている低位舌のケースや舌全体や舌根(舌の根元)が大きいケースは、気道が塞がりやすいため「睡眠時無呼吸症候群」を発症する可能性が高めです。鼻炎や花粉症などで鼻がつまりやすい方も留意してください。
就寝時間に問題はないのにしっかり寝た気がしない方や、起床時にお口が渇いている方は、気づかぬうちに「睡眠時無呼吸症候群」になっているかもしれません。
ご家族やパートナーと一緒に暮らしている方は、睡眠時の様子を聞いてみるといいでしょう。一人暮らしの方は、この機会にスマートフォンの録音機能やアプリを利用して、呼吸やいびきの様子をチェックしてみてはいかがでしょうか。
カテゴリー: 豆知識
お子さんの歯並びが悪くなる原因は指しゃぶり!?
2024年2月28日 (水)
長期の指しゃぶりは歯並びに悪い影響を与えることをご存じですか?
本来指しゃぶりは成長過程において大切なものであるため、3歳までは生理的なものとして捉えますが、5歳をすぎると歯並びに影響することから、それまでにやめることがベストと言えます。
歯並びの問題として「上顎前突」「開咬」「狭窄歯列弓(きょうさくしれつきゅう)」の3つが挙げられ、一般的に「出っ歯」と言われる状態を上顎前突、奥歯で噛んだときに上下の前歯の間が開いている状態を開咬、歯列の形がU字ではなくV字になっている状態を狭窄歯列弓と言います。見た目やかみ合わせに問題があると、審美面だけでなく健康面にも悪い影響を与えるため、長期の指しゃぶりを防ぐことが大切です。
指しゃぶりがやめられない主な理由には「退屈」「寝付きの悪さ」「ストレス」などが考えられます。とくに5歳以降はストレスが原因となっている可能性が高めです。できるだけ指しゃぶりがおこらないような環境作りを心がけましょう。
お子様の指しゃぶりを止めるおすすめの方法は、こまめにコミュニケーションを取りながら、少しずつ指しゃぶりのデメリットを理解してもらうことです。いつやめるか目標を立てて頑張ってみるのもいいでしょう。また手をつなぎながら添い寝をしてあげると安心感が増し、指しゃぶりがおこりにくくなりますのでぜひお試しください。叱ったり、指に嫌な味がするものを塗ったりすると、余計にストレスを感じてしまい、逆効果となる恐れがありますので、あまり推奨しません。「納得してやめてもらう」ことがとても大切です。
カテゴリー: 豆知識
うがいは風邪予防だけでなく、表情筋も鍛えられる!
2024年1月25日 (木)
お口に水を含んで唇や頬を膨らませて行う「ブクブクうがい」は、どのくらいの頻度で行っていますか?
ブクブクうがいはガラガラうがいとは違って、お口の中から水が漏れるのを防ぐために自然と唇に力が入るだけでなく、頬を動かして行います。口周りの筋肉をしっかり使うことから、洗浄や殺菌効果だけでなく表情筋のトレーニングとしても最適です。
表情筋を鍛えることでお顔の見た目を若々しく保てるほか、唇がしっかりと動いて発音がよくなります。また、飲食物を飲み込む動作にも表情筋が関わっており、鍛えると誤嚥(飲み込んだものが胃ではなく肺に入ってしまうこと)の予防にも効果的です。ボーっとしているときにお口がポカンと開きやすい小さいお子様はもちろん、飲み込む機能が低下しがちな高齢者の方のトレーニングにも向いているので、ぜひご家族全員で習慣化してください。
ガラガラうがいは、お口を開けた状態で上を向き、喉を中心に洗う方法を指しますが、歯や舌のすき間などにはうがい薬が入りにくいため、お口の中ではなく喉の洗浄・殺菌として効果を発揮します。うがいで表情筋を鍛えたい方は、ぜひガラガラうがいだけでなくブクブクうがいも合わせて行いましょう。
カテゴリー: 豆知識
よく噛むことで若返りホルモンが分泌される!?
2023年11月30日 (木)
「よく噛む」という習慣は胃腸の働きを助けるだけでなく、表情筋を鍛えてお顔の印象を良くしたり、唾液の分泌を促したりなど多くのメリットがあります。今回は唾液の分泌量が増えることで得られる「若返り」についてご紹介します。
食文化の変化により、昔にくらべて顎が小さく細い方が増えてきました。硬い食べ物を苦手とする方や、時間に追われて食事をゆっくり楽しむという方も少なくなった印象です。しかし、実は唾液に含まれている「パロチン」という成分は皮膚の新陳代謝を活発化する働きを持っており、分泌量が増えればそれだけ若返り効果が期待できます。全体を使ってしっかり噛むことで表情筋がバランスよく鍛えられて左右対称の見た目になることも、美容面では大きなメリットといえるでしょう。
若い方のなかには、しっかり噛むことを「顎が大きくなり見た目が悪くなる原因」と捉えている方もいますが、顎骨が成長するのは6〜12歳であり、受け口やしゃくれなどの原因ではありません。偏食やしっかり噛まない食生活を送るほうが、歯並びの崩れやお顔の歪みにつながるため、美容面では不利といえます。ぜひこの機会に歯応えのあるものを時間をかけて食べてみませんか?
しっかり噛むことを今日から習慣化して、全身の健康と若々しい見た目を維持しましょう。
カテゴリー: 豆知識
Copyright © Shirakawa dental clinic All rights reserved.