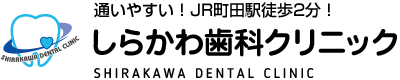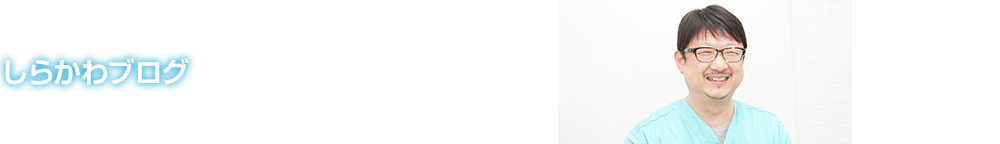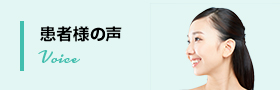歯周病が口臭の原因に!?効果的な予防対策とは
2023年2月14日 (火)
口臭はさまざまな原因で発症します。なかでもとくに口臭の原因となりやすいのが歯周病です。歯周病とは、プラークの蓄積によって細菌が繁殖し、歯肉に炎症が起きたり歯を支える骨が溶けたりする病気として知られています。歯周病になるとメチルメルカプタンというガスが発生するため、玉ねぎが腐ったような強い臭いが発生することが特徴です。歯周病を予防するためには、歯についた汚れやプラークをしっかり取り除くことが大切です。そのためにも、歯ブラシだけで終わらせずフロスを使用する習慣をつけましょう。歯ブラシだけで歯の隙間の汚れやプラークまで取り除くことはできません。
また、夜だけではなく毎食後に歯磨きすることも大切です。食後は口の中の細菌が繁殖しやすくなっているので、食後は丁寧に歯磨きをしましょう。しかし、フロスを使っても毎食後に歯磨きを行っても歯周病になるリスクをゼロにすることはできません。そこで有効なのが、歯周病予防のために歯医者に通うことです。歯医者といえば症状が出てから通う場所というイメージをもっている方が多いかもしれませんが、実は予防のために通う場所でもあります。歯石を取り除いたり、歯に溜まっている汚れを取ったりすることで歯周病の予防が可能です。歯石取りは3~6か月に1度の頻度で行うのが最適ですので、定期的に歯石を取り歯周病の予防をしましょう。
カテゴリー: 歯周病
歯周病と全身の病気の関係とは
2022年11月29日 (火)
ひとつ疾患があると、他のさまざまな全身疾患との関連を指摘されることが少なくありません。ご多分に漏れず、歯周病もまた全身疾患を深く関連しているのです。なぜ歯周病が全身疾患を引き起こし、また、全身疾患の方も歯周病を悪化させるのでしょうか。
歯周病と心疾患
歯周病が悪化すると、歯ぐきで歯周病菌が増殖し、血流に混ざって心臓へ到達します。やがて、血液を介して心臓の内側にある膜や弁に歯周病細菌が感染することで炎症が発現し、心不全を発症する確率が上昇します。
また、心臓の血管に歯周病菌が付着し、血中のフィブリノーゲンが増加して血液がドロドロになり、血栓が形成されやすくなります。
歯周病とメタボリックシンドローム
高血圧・脂質異常などの生活習慣病では脂肪が増えると炎症性物質が作られます。これによって動脈硬化が発現します。
メタボリックシンドロームに歯周病が合併すると、さらに体内の炎症反応が増強します。
脳卒中や心筋梗塞は命の危険につながり、後遺症が残ると不自由な生活を強いられます。
歯周病と低体重児出産
妊娠中に歯周病にかかると低体重児出産や早産の確率がアップし、早産の50%以上が歯周病感染によるとも言われます。
歯周病菌が増殖することにより、炎症性物質が過剰に分泌されます。歯ぐきの血管から炎症性物質が侵入し、子宮の収縮運動を促進して早産や低体重児出産を引き起こします。
カテゴリー: 歯周病
日頃から歯周病の予防をしたほうが良いの?
2022年8月16日 (火)
「歯周病にはなりたくないけど、どのくらい予防をしたらいいの?」と疑問に感じたことはありませんか?
今回は、歯周病の予防の頻度と、その理由について分かりやすくご紹介します。
歯周病には毎日の予防が大切です
お口トラブルの一つである歯周病は、歯の周囲の組織が菌に感染する病気です。
歯ぐきにのみ問題がみられる軽度の状態を歯肉炎(しにくえん)、進行して歯をささえる歯槽骨(しそうこつ)にまで問題が生じた状態を歯周炎(ししゅうえん)といいます。歯周病という呼び方は、歯肉炎と歯周炎の総称です。
毎日の予防が必要な理由を以下にまとめました。
痛みを感じないまま悪化する
歯周病は虫歯とはちがい、ほぼ痛みを感じることなく進行し、どんなに悪化しても違和感程度で済んでしまいます。
骨を溶かされると治すのが難しい
軽度の歯肉炎であれば、お手入れ方法の見直しと、数回のクリーニングで治ることが多いのですが、歯槽骨を溶かされる歯周炎になると一気に治療が難しくなります。場合によっては手術をしなくてはいけません。
口臭が強くなる
歯周病が悪化すると、腫れや出血だけでなく、膿(うみ)が出てくる症状がみられるケースも少なくありません。
それによって「少し離れていても分かるほどの強い口臭」がでることもあるため、注意が必要です。
毎日のケアで歯周病を予防しましょう
どんなに歯を磨いても、歯ぐきに汚れがついている状態では歯周病を予防できないので、歯の根元を歯ぐきもふくめて丁寧に磨いてください。1度きれいにしても食事をすれば汚れは再びつくため、毎日続けることが大切です。
冷たいものを飲んだ時に歯がしみるのはどうして?
2022年4月14日 (木)
よくあるケースは、虫歯になって歯の表面に穴が開き、神経がむき出しになった部分に冷たいものや酸味の強いものが触り、痛みとなって感じられる状態です。
一方で、冷たいものを口にふくんだ時、虫歯がないのに歯にズキーンと言う衝撃が走る経験をされたこともあるのではないでしょうか。これは、まさに、「知覚過敏」であり、正式には「象牙質知覚過敏症」という状態です。冷たいものを食べたり飲んだりしたときにズキンとするほどの強い衝撃でなくても、歯が浮くような違和感を感じたら、やはりそれは知覚過敏です。テレビで歯みがき剤のCMとして聞いたことがあると思いますが、どのような状態によって発症するのでしょうか。
この象牙質知覚過敏症は、歯ブラシの使い方が適切でないことが一因で、歯根(歯の根元の部分)がすり減ったり、歯周病などで歯ぐきがやせて下がったり、歯の根元が露出していたりする状態が根底にあります。
本来、健康な状態ならば歯肉の中に隠れている歯根が表面に露出し、毎日の歯磨き時にブラシングで削られて神経に刺激が伝わってしみるのです。
他にも、長年続く睡眠時の歯ぎしりや食いしばりで歯の一部が欠けてしまったり、根元の歯質がはがれてしまったりすることがあります。これも神経が露出し、冷たいものがしみる原因の一つです。
歯がグラグラするのはなぜ?その原因と対処法について
Copyright © Shirakawa dental clinic All rights reserved.